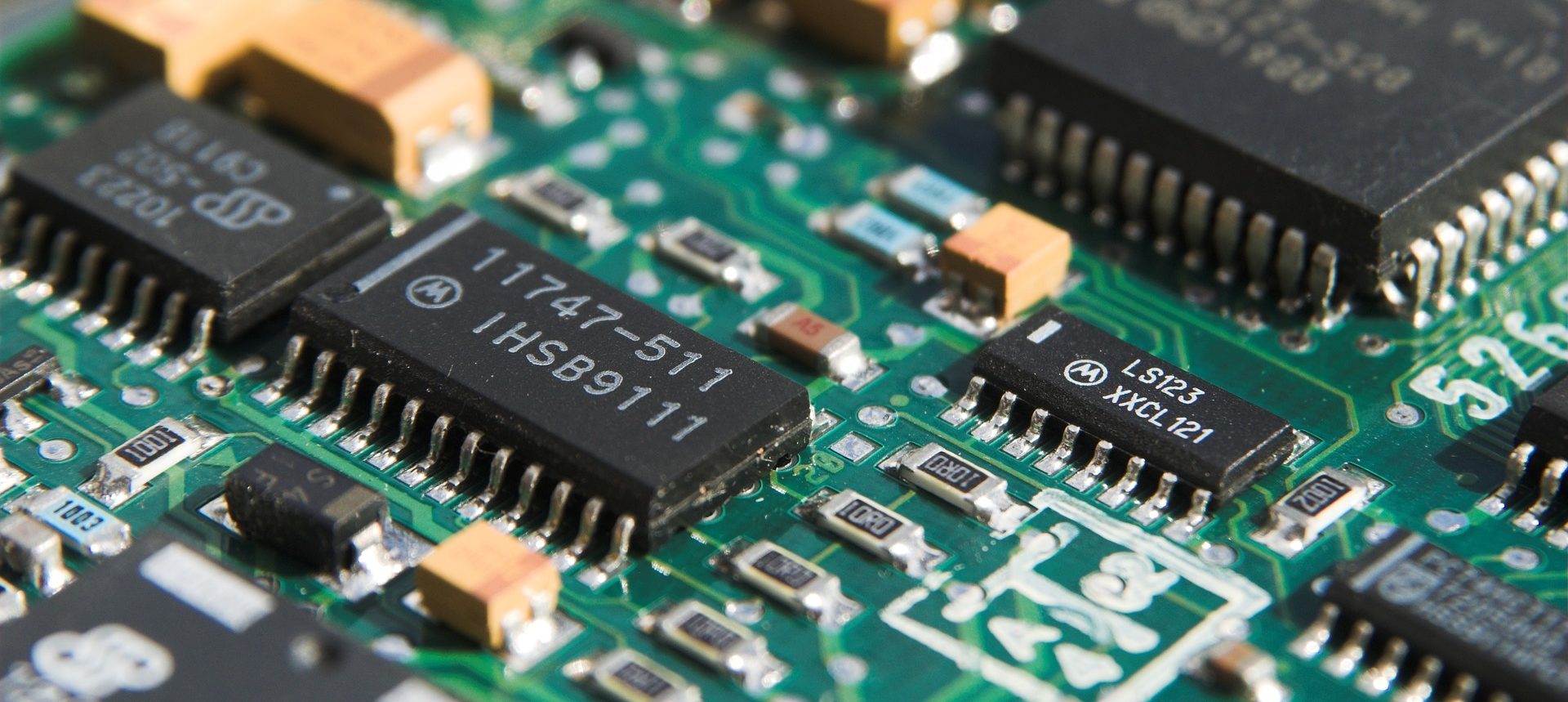いよいよ2020年から小学校でプログラミング教育が必修化されます。
小学校の現場ではこれまで自主的に取り組んできた教員以外は、プログラミング教育に対して理解が不足していて、混乱したり不安を抱いたりしているようです。
このサイトでは管理人が取り組んできたプログラミング教育の実践を通して、どんなことをやればいいのか、どんなことができるのか考えていきたいと思います。

1 なぜプログラミング教育を導入するのか
文科省の「小学校プログラミング教育の手引(第二版)」を見ると、導入の理由としてプログラミングを知ることでコンピューターの仕組みを理解し主体的に活用すること、子供たちの可能性を広げて将来社会で主体的に活躍するきっかけになることなどがあげられています。
また、プログラミング教育は学習指導要領の中で「学習の基盤となる資質・能力」と位置
付けられた「情報活用能力」の育成や情報手段(ICT)を「適切に活用した学習活動の充実」を進める中に位置づけられています。
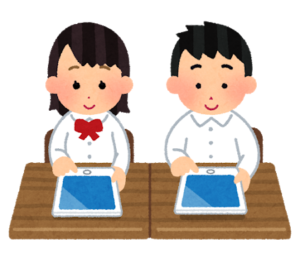
2 どんなことをやればいいのか
実は具体的な内容については、他の教科と違ってあまり明確に決められてはいません。
プログラミング教育にかかわる学習活動の分類として教育課程内では、
A 学習指導要領に例示されている単元等で実施するもの
B 学習指導要領に例示されてはいないが、学習指導要領に示される各教科等の内容を指導する中で実施するもの
C 教育課程内で各教科等とは別に実施するもの
D クラブ活動など、特定の児童を対象として、教育課程内で実施するもの
が示されていますが、具体例はAで5件、BとCは4件ずつしかありません。
文科省・総務省・経産省と民間企業が協力して立ち上げた「未来の学びコンソーシアム」のポータルサイトを見ると、学習指導要領に示されたもの以外にも実践事例が掲載されていますが、まだまだ十分な数とは思えません。各分野でのいろいろな実践が数多く集まることが望まれます。